どうする家康のあらすじ。
弘治2年(1556年)の駿府。三河国の松平次郎三郎元信は今川義元のもとでのどかな人質生活を送っていた。
次郎三郎は親の七回忌に石川数正、鳥居元忠、平岩親吉と三河に戻り、三河衆に歓迎される。
駿府に戻った次郎三郎は義元のはからいで瀬名を娶り、名を元康と改める。
永禄3年(1560年)、織田信長の大高城攻めに今川は出陣、元康は兵糧運びを命じられる。
元康と三河衆は敵軍を突破し大高城に入るが、義元は桶狭間で信長に討たれる。
信長を恐れる元康は駿府に戻ろうとするが、三河衆から猛反対され、悩んだ末三河の岡崎城に入り、松平家当主となる。
松本潤が演じる『徳川家康』とは?
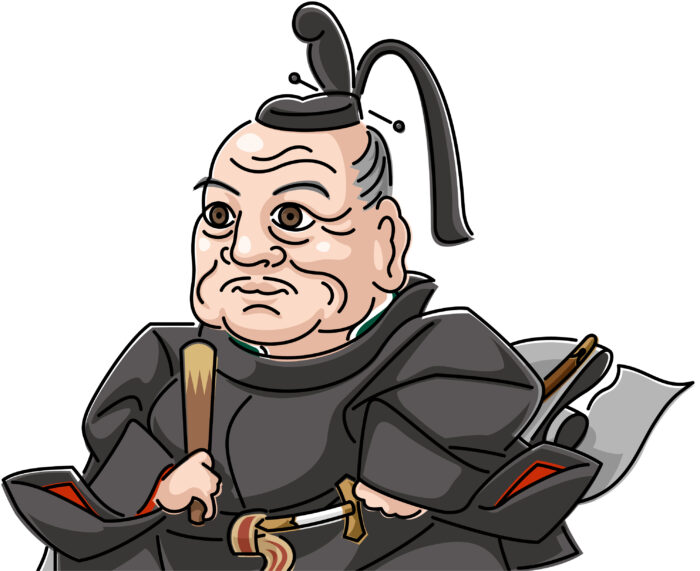
徳川家康は、日本の江戸時代初期に活躍した武将・大名で、徳川幕府の初代将軍として知られています。
家康は、1543年に遠江国(現在の静岡県)に生まれました。父親は松平清康、母親は於大の方という人物でした。家康は若い頃から戦に明け暮れ、戦術や政治手腕を磨いていきました。
1590年、豊臣秀吉による小田原征伐により、東国の領地を失うことになった家康は、東北地方に移って越後国の新潟城に入り、北陸方面から侵攻する軍勢を迎え撃ちました。これが、後の関ヶ原の戦いに繋がっていきます。
1600年の関ヶ原の戦いにおいて、家康は西軍と対決し、勝利を収めます。その後、江戸幕府を開き、徳川家は将軍を代々務めることになりました。
家康は、江戸幕府を創設し、平和な時代を築くための制度を整え、政治・文化の発展に力を注ぎました。また、武士の道徳心や人間性にも注目し、『武鑑』という武士の修養書を執筆しています。
1605年に死去した家康は、江戸にある日光東照宮に葬られ、今でも多くの人々から尊敬を集めています。
徳川家康が開いた『徳川幕府』
徳川幕府は、日本の江戸時代に存在した武家政権で、徳川家康が開いた江戸時代の支配体制です。1603年、家康が将軍に就任したことを契機に、江戸幕府が成立しました。
江戸幕府は、全国の領主や藩主を統括する中央政府として、地方支配者や民衆の支配を強化し、専制的な政治を行いました。また、幕府は儒教を基盤として、社会秩序を維持するために様々な政策を実施し、商業や産業の発展を促進しました。
江戸時代は、武士が支配する社会であったため、武士道や礼儀作法が重んじられました。また、文化や芸術、科学技術の発展も見られ、木工技術や鍛冶技術などの工芸品や、浮世絵や歌舞伎などの芸術文化が栄えました。
幕府は、1867年に大政奉還が行われ、明治維新によって武家政権が終焉を迎えましたが、その後の日本の発展に大きな影響を与えた政権であるとされています。

どうする家康 前編 NHK大河ドラマ・ガイド
家康が葬られている『日光東照宮』
日光東照宮(にっこうとうしょうぐう)は、日本の栃木県日光市にある神社で、徳川家康を祀った東照宮の総本社です。徳川家康が死去した後、江戸幕府3代将軍徳川家光によって建立されました。
日光東照宮は、豪華な装飾と建築美で知られ、国宝や重要文化財の建物や美術品が数多く保存されています。特に、本殿の彫刻や、華麗な彫刻や金箔を施された「眠り猫の石塔」が有名で、多くの観光客が訪れる人気のスポットとなっています。
日光東照宮は、世界遺産に登録されており、日光の奥社とともに「日光の社寺」として観光地としても有名です。
大河ドラマ
「大河ドラマ」は、NHKが制作・放送する、日本の歴史をテーマにしたテレビドラマのシリーズです。
1963年に第1作「花の生涯」が放送され、現在までに60作品以上が制作されています。
歴史上の人物や事件、時代背景を取り上げ、豪華なキャスト陣や美しい映像、ドラマチックなストーリー展開などが特徴です。
代表的な作品としては、「義経」「太閤記」「真田丸」「おんな城主 直虎」などがあります。
これらの作品は、日本史を学ぶ上での教材としてだけでなく、豊かな感性や想像力を刺激するドラマとしても親しまれています。
また、出演者やスタッフの努力や、ドラマの影響で、観光地の人気が高まることもあります。
